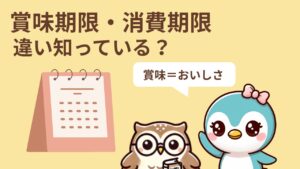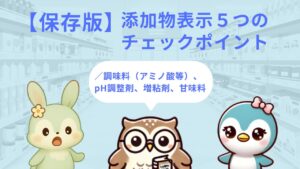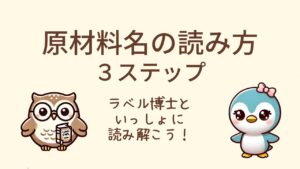食品ラベルでよく目にする「原産国」「原産地」「原料原産地」。
言葉は似ていますが、実は対象となる食品も決まり方もそれぞれ異なります。
「国産だから全部日本のもの」と思っていても、原料は外国産だった…ということも少なくありません。
そこで今回は、食品表示検定の試験対策にも役立つように、3つの用語を整理してわかりやすく解説します。
生鮮食品に表示されるのは「原産地」
キャベツ、きゅうり、トマトなどの「農産物」、牛肉・豚肉・鶏肉などの「畜産物」、あじ・さけ・いか・くるまえびなどの「水産物」。
これらの生鮮食品には、その食品が「収穫・飼育・漁獲された場所」を原産地として表示します。
 ラベル博士
ラベル博士『どこで育ったか・とれたか』を示すのが原産地表示なんじゃ。
消費者が食品を選ぶときの大切な判断材料になるため、必ず表示しなければならない義務表示になっておるぞ。
農産物の場合
農産物(キャベツ、きゅうり、トマトなど)は、収穫された場所が原産地です。
- 国産品
都道府県名を表示(例:群馬県)
また一般的に知られている地名(例:屋久島、信州)での表示も可能です。 - 輸入品
原産国名を表示(例:オーストラリア)
また一般的に知られている地名(例:カリフォルニア州)での表示も可能です。
■表示例
- 国産品
名 称 キャベツ
原産地 群馬県 - 輸入品
名 称 オレンジ
原産地 オーストラリア
畜産物の場合
畜産物(牛肉・豚肉・鶏肉など)は、飼育された場所が原産地です。
複数の場所で飼育された場合は、最も長く飼育された場所を表示します。
- 国産品
国産と表示しますが、都道府県名や地域名(例:鹿児島県、九州)ででの表示も可能です。
また一般的に知られている地名での表示も可能です。 - 輸入品
原産国を表示
■表示例
- 国産品
名 称 鶏もも肉
原産地 国産 - 輸入品
名 称 牛かたロース
原産地 アメリカ
水産物の場合
水産物は、漁獲された場所または養殖された場所が原産地です。
- 国産品
基本は「水域名」を表示(例:日本海西部)。
水域名の表示が困難な場合は、水揚げした港名や都道府県名で表示できます。
また、水域名に加えて港名や都道府県名を併記することも可能です。 - 輸入品
原産国名を表示。ただし「ノルウェー(大西洋)」のように水域名を併記することもできます。
■表示例
- 国産品
名 称 まあじ
原産地 日本海西部
※都道府県名を併記
原産地 日本海西部(長崎県) - 輸入品
名 称 さば
原産国 ノルウェー
※水域名を併記
原産地 ノルウェー(大西洋)
加工食品で”輸入品”に表示されるのは「原産国」
輸入された加工食品には、最終的に加工・製造した国を「原産国」として表示します。



輸入品は原産国名が必ず表示されておるんじゃ。
■表示例
- 輸入品
名 称 チョコレート
原産国 フランス
国産の加工食品は原産国は記載しない?
「日本で作られた加工食品なのに『原産国:日本』と書かれていないのはなぜ?」と思うかもしれません。
国産加工食品は、製造者名と住所を表示するルールがあるため、そこで国内製造であることが分かります。
そのため、あえて「原産国:日本」とは表示されません。
一方で輸入品は、輸入者の表示だけでは製造国が分からないため、必ず原産国名を表示することが義務になっています。
加工食品で”国産品”に表示されるのは「原料原産地名」
国内で製造された加工食品には、重量割合が最も多い主原料の産地を表示するルールがあります。
この「主原料」が生鮮食品の場合と加工食品の場合とで、表示の仕方が少し異なります。
- 主原料が生鮮食品の場合
その生鮮食品の「原産地」を表示します。 - 主原料が加工食品の場合
その加工食品の「製造国(原産国)」を表示します。
■表示例
- 主原料が生鮮食品の場合
名 称 豆腐
原料原産地名 アメリカ(大豆) - 主原料が加工食品の場合
名 称 清涼飲料水
原料原産地名 ニュージーランド製造(オレンジ果汁)
消費者が実際によく目にするのは、この「原料原産地表示」です。
「生鮮品の産地」と「加工食品の製造国」のどちらが表示されているのかを意識して見ると、ラベルの理解がぐっと深まります。
3つの用語を整理すると…
| 用語 | 対象食品 | 決まり方 |
|---|---|---|
| 原産地 | 生鮮食品 | 収穫・漁獲・飼育地 |
| 原産国 | 加工食品 | 最終加工・製造した国 |
| 原料原産地 | 加工食品の主原料 | 主原料が生鮮食品ならその産地 主原料が加工食品ならその製造国 |
原産地・原産国・原料原産地を整理して覚える
原産地・原産国・原料原産地の違いを整理すると、それぞれが「食品を選ぶときの見方の軸」であることがわかります。
生鮮食品なら「育った場所」、加工食品なら「作られた国」、国産加工食品なら「使われている原料の産地」。
同じ「産」の字がついていても、意味合いは大きく異なるのです。



試験のときも実生活のときも、『何を基準に表示しているのか』を意識すると理解が深まるんじゃ。



私は買い物のとき、原料原産地を見て“自分に合うかどうか”を確かめているよ。ちょっとした意識が、安心につながるんです。
食品ラベルを読むときに「どの視点で書かれているか」を押さえておけば、誤解なく正しく理解できます。
検定本番でも迷わず答えられるだけでなく、日々の安心にもつながります。