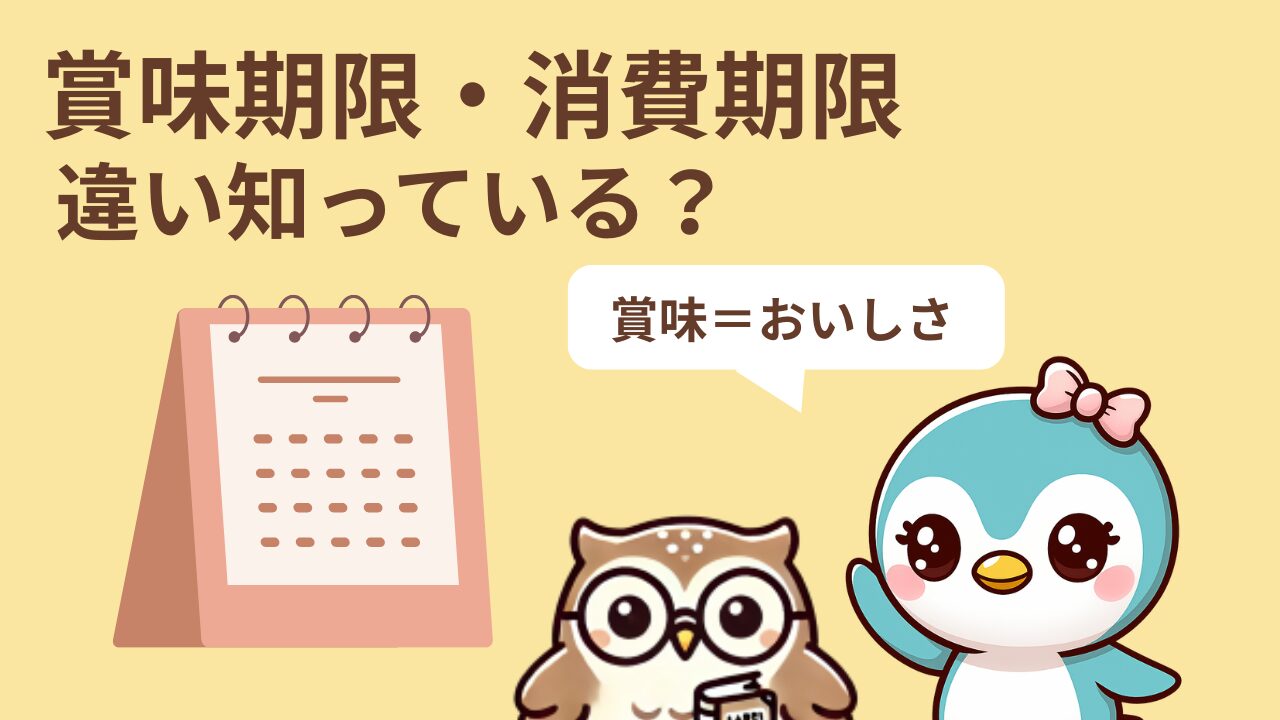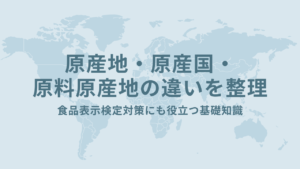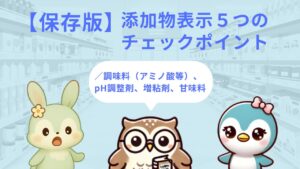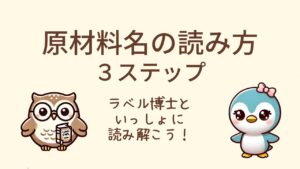「これって、もう食べちゃダメなのかな?」
賞味期限や消費期限を見て、そんなふうに迷ったことはありませんか?
なんとなく不安で捨ててしまったり、まだ食べられるのか悩んだり‥‥
でも、実はこの「期限表示」には、ちゃんとしたルールと根拠があります。
今回は、賞味期限と消費期限の違いから、表示の見つけ方、コンビニでの工夫や制度の見直しまで、知っておくと役立つ“期限表示の見方”を、やさしくご紹介します。
「賞味期限」と「消費期限」の違いって?
なんとなく知っているようで、実はあいまいな人も多いこの2つ。
まずは、期限表示の基本から整理してみましょう。
食品のパッケージには、次のいずれかの期限が表示されています。
| 表示名 | 言葉の意味 | 内容 | 対象食品の例 |
|---|---|---|---|
| 賞味期限 | 「賞味」は“たのしむ・味わう”の意味 | おいしく食べられる期限(=品質の目安) | スナック菓子、缶詰、冷凍食品、レトルトなど |
| 消費期限 | 「消費」は“使い切る・消費する”という実用的な意味 | 安全に食べられる期限(=衛生面のリミット) | お弁当、生菓子、サンドイッチ、惣菜など |
- 賞味期限は「この日までなら、風味や食感などのおいしさが保たれていますよ」という “おいしさの保証”
- 消費期限は「この日までなら、安全性が確認されています」という “食中毒リスクの回避ライン”
 ラベル博士
ラベル博士簡単に覚えるなら、“賞味=おいしさ”、 “消費=安全”じゃな。
どちらの表示も、「定められた保存方法」で保管されていることが前提です。
たとえば「10℃以下で保存」などの条件が書かれている場合、それを守っていなければ、期限表示の意味はなくなってしまいます。
期限表示はどこに書いてある?どう探す?
実際に食品を手に取って、「あれ、どこに書いてあるの?」と迷ったことはありませんか?
基本的に、賞味期限や消費期限は「一括表示欄」に記載されています。
この欄には、名称・原材料・内容量・保存方法など、表示の基本情報がギュッと集められています。
ただし、商品の形やスペースの関係で、期限だけが別の場所に書かれていることもあります。
その場合、一括表示欄には、次のような案内が書かれているのが一般的です。
- 「枠外右下に記載」
- 「枠外上部に記載」
- 「裏面右下に記載」



“枠外右下に記載”って書いてあったから見てみたら、本当に裏に書いてあった。
このように、まず一括表示欄を見て、表示位置の案内を確認するのがポイントです。
パッケージのあちこちを探すよりも、案内を手がかりにするとスムーズに見つけることができます。
表示ルールは法律でしっかり決まっている
期限表示には、食品表示基準という法律に基づいたルールがあります。
その一部をご紹介すると・・
- 表示は必ず日本語で記載すること
- 「年 → 月 → 日」の順に明記すること
(例:2025年8月20日) - 製造から3か月を超える賞味期限は、「年月」表示でも可
(例:2025年12月) - 文字サイズは原則8ポイント以上
ただし、容器包装の表示面積が150 cm²以下の場合は、5.5ポイント以上でもOK - 一括表示欄に入らない場合は、表示位置の案内が必要
(例:「枠外右下に記載」など)
こうした表示は、消費者が正しく理解し、安心して選べるようにするための「ルール」です。
コンビニのおにぎりは「時間」まで!
~ロスと安全のせめぎあい~
コンビニのおにぎりやお弁当をよく見ると、
「25.07.23 23時」のように、“時間”まで細かく書かれているのに気づくことがあります。
これは、傷みやすい食品の安全ラインを、明確に示すための工夫です。
とくに高温多湿の夏場は、数時間の差で食品の状態が変わることもあります。
そのためコンビニでは、製造・納品・販売・廃棄のタイミングをすべてシステムで時間管理しているのです。



全国どこの店舗でも、同じルールで運用するには “時間表示” が必要なのじゃ!
無添加志向が賞味期限を短くする?
あるメーカーの品質管理担当者は、こんな話をしてくれました。
無添加を求める声が強くなり、保存料やpH調整剤を使わなくなったことで、
菌のリスクが高まり、結果的に賞味期限を短くせざるを得なくなった食品もあります。
そして、廃棄も増えてしまう…。そんなジレンマもあるんです
“無添加”という言葉の響きは安心感がありますが、保存性や安全性をどう確保しているのかまで目を向けることも、賢い食品選びにつながっていきます。
賞味期限=腐る日、ではない!
~“期限切れ”をどう考える?~
ここで、よくある誤解を一度整理しておきましょう。
賞味期限は「腐る日」ではありません。
賞味期限とは、その食品が「おいしく食べられる」と企業が保証する期限。
つまり、品質の目安であり、「この日を過ぎたら食べてはいけない」というものではないのです。
企業はこうして“おいしさ”を保証しています
賞味期限は、以下のような手順を経て決められています。
- 保存試験:温度や湿度を変えて、どのくらい品質が持つかを検証
- 官能検査:味・香り・見た目などの「おいしさ」を人の感覚でチェック
- 微生物検査:菌が増殖していないか、安全性を科学的に評価
そのうえで、設定された日数に対し、安全係数(例:0.8)をかけて、実際の表示は“かなり余裕を持たせた日付”になるのが一般的です。



たとえば実験で100日大丈夫だったら、80日にして賞味期限を設定する。つまり、少し過ぎてもすぐダメになるわけではないんじゃ!
食べられるかどうかの見きわめ方
では、賞味期限を過ぎた食品は、すぐに捨てるべきなのでしょうか?
じつは、以下の条件を満たしていれば、食べられるケースもあります。
- 未開封であること
- 保存条件(温度・湿度など)を守っていること
- におい・見た目・味に異常がないこと
これらを総合的に見て「問題ない」と判断できる場合は、賞味期限を少し過ぎても食べられる可能性があります。
ただし!
消費期限は安全性に関わるリミットなので、過ぎたら基本的に食べてはいけません。
安全率から見直し?新ガイドラインでは「安全係数の目安を削除」
~消費者庁の新しい動き~
これまで、賞味期限の設定には「安全係数(例:0.8)」をかけて、かなり余裕を持たせた日付にするのが一般的でした。
しかし、2025年、消費者庁はこの“安全率”の考え方について、大きな方針転換を打ち出しました。
2025年、消費者庁は賞味期限の設定ガイドラインを見直し、「安全係数0.8以上」の目安を削除する方向を打ち出しました。
参考:食品期限表示の設定のためのガイドライン」見直しの方向性(案)
新しい方針では、以下のようなポイントが示されています
- 食品の特性に応じて、安全係数は柔軟に設定してよい
(例:腐りにくい食品は係数を1に近づけてもOK) - リスクの低い食品(缶詰・レトルト食品など)には、安全係数を設けなくても可
- “まだ食べられる目安”などの情報提供も推奨
つまり、「科学的に問題がなければ、過度に短くしなくていい」という、現実的かつ合理的な見直しが進んでいるのです。



これまでの“安全係数0.8”は、かなり余裕を見ておったが、無駄な廃棄が出るなら見直していこうという動きじゃな。
期限表示は「食品の未来」を考えるヒント
ここまで見てきたように、期限表示は「食べられる・食べられない」を判断するだけのものではありません。
その裏には、食品の安全性、品質管理、企業努力、環境配慮など、たくさんの想いと仕組みが詰まっています。
- 「「期限=ただの線引き」ではなく、「安全と安心の目印」
- 「無添加=安心」と決めつけず、「どうやって安全性を保っているか」に注目
- 「すぐ捨てる」から、「見て・考えて・活かす」へ



これからは、“期限=終わり”じゃなくて、“上手に使うためのサイン”って思ってみるのがいいかも!
食べものを、大切に。表示を、味方に。
私たちが「ラベルの意味」を少しだけ知ることで、食べものを無駄にせず、安全においしく楽しむことができます。
期限表示は、ただの数字ではありません。食品の未来と、私たちの選び方をつなぐ小さなサインです。
今日から少しだけ、表示ラベルを見てみませんか?きっとそこには、「大切にする」ヒントが詰まっています。



なんだか難しそうだったけど、“賞味期限=おいしさのしるし”って思うと、ちょっと仲良くなれそうかも!



ふむ、表示は“気にする”ものではなく、“味方にする”ものじゃな